秋刀魚の塩焼きは秋の味覚!不思議な生態と内蔵まで美味しいその訳は?

秋の味覚と言えば秋刀魚の塩焼きですよね!
また、缶詰も美味しく保存食としてもポピュラーで値段も安いです。
七輪でゆっくり炙って大根おろしとすだちがあればもう言うことなし!
日本を代表する美味しい魚と言えるでしょう。
でも秋刀魚の生態って未だによく分かっていないっていないらしいです。
そしてなぜあんなに美味しいのか?
気になったので調べてみました。
スポンサーリンク
Contents
あまりにも身近な秋刀魚ってどんな魚?
秋刀魚(サンマ)は、ダツ目サンマ科に属し、動物プランクトンをメインとして捕食し、雑食性です。
そしてイワシやアジと同じで「多獲性浮魚類」と呼ばれています。
これは大群で海の表層を泳ぎ、漁で大量に捕獲されるからです。
今まで秋刀魚は水産資源として身近な存在でしたが、その生態は謎に包まれていました。
近年、秋刀魚の養殖が進み少しずつその謎が明らかにされてきました。
秋刀魚は北太平洋黒潮域で産卵、北上し親潮域で大きくなり、秋に日本の太平洋沿岸を南下する途中で捕獲されます。
今までなぜ秋刀魚の研究が進まなかったかというと、秋刀魚はアメリカ沿岸を含む太平洋全域を活動域としていて調査範囲があまりにも広大だったのと、光や音に大変敏感なため、研究用として飼育しようとしても壁に激突して死んでしまうなどして困難を極めたのが主な理由でした。
秋刀魚の卵は直径1.5~2.2mmぐらいの透明なぶどう状です。
秋から冬に卵から10日程で孵化した稚魚は、およそ一年かけて30cmほどの大きさになります。
地道な研究調査により、秋刀魚の寿命はおよそ2年ほどだということが解ってきました。
今、アジアの様々な国が秋刀魚漁を拡大し、捕獲高もグングン上昇しています。
このままだと貴重な水産資源の枯渇という可能性も考えられます。
そのため、日本では秋刀魚の完全養殖に向けて急ピッチでこうした研究が行われているのです。
秋刀魚の漢字の由来は?
秋刀魚は秋に穫れる刀のような魚だから秋刀魚という漢字が当てられました。
比較的最近にようですね。
魚は季節を表す漢字が当て字としてつけられることが多いです。
春告魚(メバル)なんかも有名ですよね。
野鳥と一緒で、日本の四季に合わせた生命サイクルがあるからでしょう。
これらネーミングを持つ生き物を昔から息づく日本情緒の一端だと思って見れば、なんとも言えない奥ゆかしい世界に入って行ける気がします。
何故秋刀魚はあんなに美味しいのか?
DHA,EPAをはじめとする栄養満点で良質なタンパク質の固まりである自然健康食品の秋刀魚ですが、なぜあんなに美味しいのでしょうか?
それは食べ頃となる9月頃、秋刀魚の脂肪が10%~20%にもなるためです。
たっぷり油が乗った秋刀魚が一匹200円以下で買えるという奇跡。
そして極めつけはハラワタのうまさ。
新鮮な秋刀魚のハラワタは、そのまま食べるとウニのような甘さで全く苦くないとのこと。
ウニのようなハラワタ・・・一度食べてみたいです。
さすがに一般人は漁師さんのような機会はありませんけれども、焼いた秋刀魚のハラワタを取り除かずにそのまま食べる人が多いのです。
これは秋刀魚の消化器官の構造に答えがあります。
なんと秋刀魚は、エサを取ってから排泄までたったの30分しか掛からないのです!
人間で20時間、アジは36時間も掛かるのに対してわずか30分です。
つまり腹の中にエサを長く溜め込まないので、ハラワタを美味しくいただくことができるのですね。
秋刀魚といえば昔から季語にも使われるほど日本文化に深く根ざした庶民の魚です。
豊かな食に感謝して、パタパタとうちわで七輪を煽って、いつまでも美味しい秋刀魚をいただきたいものですね。
関連記事です
自然探検☆水の惑星アウトドア紀行
コメント
この記事へのトラックバックはありません。































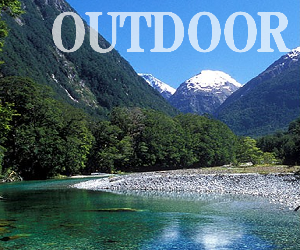
この記事へのコメントはありません。