武士の一分に通ずる磯釣りの精神と文化

磯釣りに文化あり。
磯釣りは歴史ある庄内武士たちに昔から受け継がれてきた釣りなのです。そんな磯釣りを武士たちの視点から見てみます。
スポンサーリンク
Contents
武士の一分としての釣り
その昔、山形県庄内地方では武士たちの心身鍛錬の一環としてクロダイ釣りを庄内藩主が奨励したという歴史がありました。
思い荷物を担いで長い距離を歩き、今の軽いカーボン技術では考えられないほど重い竹竿(両手でやっと持てるほどの)を長時間支え、日本海の荒波を被りながら静かに魚が掛かるのを待つという苦行を行いました。
武士たちは普段、刀を自分の命と同格に扱い大切にしてきましたが、磯釣りに使う竿も刀と同様、格別の扱いで身に付けていました。
武士の刀と同じ価値を持つものが「竿」であったということですから、やはり私たち釣り人にとって竿は時空を超えた特別な存在なのかもしれません。
彼ら庄内武士たちの歴史については山形県鶴岡市にある公益財団法人「致道博物館」に多くの資料が残されており、釣り師必見の展示物がありますので興味のある方はどうぞ。
庄内地方で行われる独自の「庄内釣り」は現代までその血筋が生きており、釣りメーカーからも庄内釣り専用の竿が販売され続けていることなど釣り業界の熱い視線が見て取れます。
木村拓哉 武士の一分として
過去に木村拓哉さん主演の「武士の一分」という映画が公開されましたが、あの盲目の武士、新之丞(木村拓哉)が怒りを抑えながら静かに剣技に魂を込めるシーンや、果たし合いで奇襲をしかける卑怯な相手の気配を察知して見事勝利を収めるラストの見せ場などは、命を落とすかもしれない危険な場所で磯釣りに懸ける極限の精神状態に通ずるものがあります。
激しく白波を立てる磯場で周りの轟音と風の触感、雑念を消し、ただゆらゆら漂うウキを見つめるというより鍼から道糸、竿先を通じて手元に感じる僅かな気配の変化を五感で察知し、いざ来るその変化に瞬時に呼応するという行いは、日本人の魂の奥底に眠る武士道精神を呼び起こすのに相応しいふるまいなのです。
そう考えると、我々日本人の血筋には「武士の一分」気質が生まれたときから備わっているのかも知れませんね。
スポンサーリンク
日本の釣り文化は
戦前、繁栄を極めた江戸城下町での釣りは上流家庭の洒落た「たしなみ」として流行していました。一般家庭において釣りはまだ気軽に行える遊びでは無かったのです。当時の釣り人の持ち物は職人による綺麗な装飾を施された小継の和竿などを始め小道具にも大変な拘りが見られ、また一つの文化を形成していきました。

今日、我々現代の釣り人は自由に釣りに出で立つことができます。
そうして昔のままの情景で糸を垂れる時、道具は変わりましたけれども、遙かなる時を超えて先人たちの残した文化、技に敬意を払い自然に感謝し環境を守り、後世に豊かな釣り文化を継承していく使命があるのかもしれませんね。
関連記事です
自然探検☆水の惑星アウトドア紀行
コメント
この記事へのトラックバックはありません。








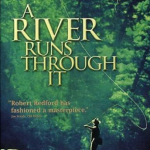





















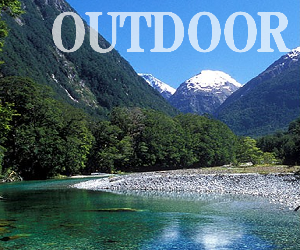
この記事へのコメントはありません。