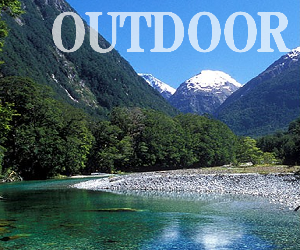安くて面白い磯竿と高くてつまらない磯竿。先調子胴調子・号数や長さの違い【悩ましき磯竿選び①】
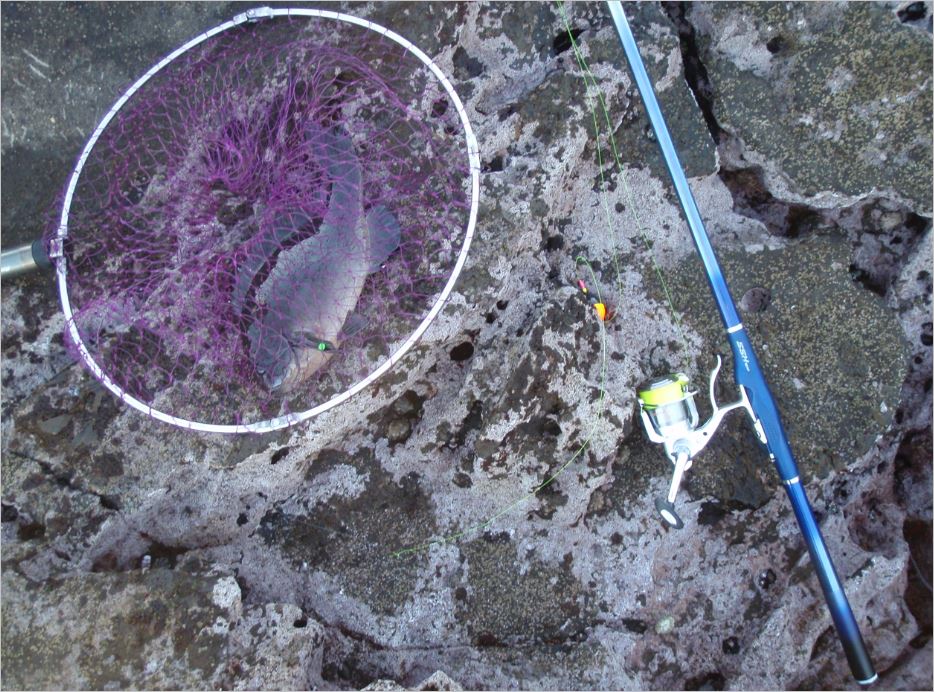
私は数ある釣り竿のなかで磯竿が最も好きです。
もちろんルアーロッドやフライロッド、それにコンパクトロッドなども好きですが、なぜか磯竿には特別なものを感じます。
しかしこの磯竿、長さも硬さも調子も素材も色々種類があって本当に悩ましいものです。そして私が最も頭を抱えている要素が「魚と駆け引きしている最中の面白さ」についてです。
今回は様々なファクターにより複雑難解な磯竿を取り巻く釣り人の感性の部分を解き明かすべく、磯竿による釣りの楽しさを要素分解してみることにします。
スポンサーリンク
シマノ・APERTO ISO XT 1.5-525が面白かった
アペルトが面白かった。ここから話を展開していきます。
アペルトとはシマノ社製の最廉価インナーガイドロッドです。今から10数年前、初めて磯釣りにチャレンジした私が最初に購入した磯竿です。この竿の大きな特徴は当時流行っていた中通し竿(道糸が竿の中を通るガイド無しの磯竿)の中で最も安かったという点でした。お金も知識も経験も無かった私はシーバスロッドや投げ竿でウキフカセの真似事をしていましたが限界が来て予算だけを釣具屋の店員に伝え磯釣り初心者らしく1.5号の5.3mクラス(アペルトは5.2m)の中通し竿を購入しました。しかしこのアペルトはもうとにかく扱いにくい竿でした(笑)。
まず重い。ずっしりと手元に伝わる重さは当時のスタンダード磯竿の中でも最重量級です。これは安いインナーガイドロッドはみんな重かったので仕方のないところです。そして次に糸の出の悪さ。これはウキフカセで使用する2Bなどのウキ負荷では軽すぎて全く糸が出ていきません。釣り始めこそなんとか出るのですが、1時間も立てばブンブン振っても糸が出ていかないのです。ブオンとフルキャストしてはじめて数メーター飛ぶという感じです。最後は目測で距離を測って手で糸を引っ張り出してから投げてました(笑)。
これらの2大欠点を克服すべくEVAグリップを付けて持ちやすく改良したり竿尻にバランサーを付けたり(最大200g!!)撥水剤を竿内部に吹き掛けたりもしましたが全く意味なしの木偶の坊でした。
今はこのアペルトはモデルチェンジし、地味な紫色から派手な赤色になりました。そしてシマノお得意の竿内部撥水技術であるハイパーリペルを竿先の一節だけ搭載してます。私は昔の地味な色のほうが好きだったのですが、新アペルトは販売も好調のようですからまぁいいでしょう。
ところでこのどうしようもないアペルトにも唯一にして最大の長所がありました。それは釣ったときの面白さでした。当時の私はメジナをろくに釣ったことがなくて、最大でも30半ばのものでした。あまり大きくはなかったのですが、このアペルトという竿で釣ると何故か楽しいのです。ハラハラ・ドキドキすると言ったほうが良いでしょうか?だから私はこう仮説を立てました。「もっと良質の磯竿を買えばもっと磯釣りが面白くなるはずだ」と。
その時よく一緒に釣りに行っていた仲間がシマノのBB-Xシリーズを使っていました。竿先も繊細すぎるほど繊細でデリケートな竿でアペルトと比べると非常に軽くて操作が楽でした。そこで私はダイワのスタンダードロッドである「初代シデン」を購入することにしました。さぁこれから磯釣りがもっと面白くなるぞ!とワクワクしながら。
非常に高性能だがあまり面白くなかった紫電1-50
このシデンという磯竿は現在4代目がリリースされています。初代紫電→紫電メガデス→メガディスハイパー→メガディスと進化しています。メガディスというネーミングセンスがどうかとは思いますが、初代から一貫してブルーを基調としたデザインはスタイリッシュで大好きです。それにダイワお得意のマッスルカーボンであるHVFカーボンを使っているのでパワーも申し分なしの良竿だと思います。
一般的には竿が柔らかいほうが面白いと言われます。そして先調子の磯竿よりも同調子の磯竿のほうがより面白いと。だから私は釣具店をはしごしてダイワ・紫電の様々なバリエーションを振り比べ店員に負荷をかけてもらって曲げて調子を見て周りました。
その時感心したのが号数による調子の違いです。磯竿と言ったらチヌ竿と違い良型メジナの強い引きに耐えられるように強めの先調子設定が多いのですが、紫電シリーズはバリエーションが豊かなため1号モデルはどちらかといえば6:4の胴調子でした。1.2号や1.5号はもちろん先調子でしたが、1号以下は防波堤や静かな漁港で浮き釣りをする設定なのでしょう。私は胴調子の竿が欲しかったので迷わず1号にしようと思いました。なぜならアペルトは1.5号で小物を釣っても少々物足りなかったのと、胴調子の方が魚の引きをより大げさに表現してくれて楽しそうだったからです。だから次の竿は1号胴調子竿を買おうと決めていました。
次に長さです。これも調子に影響しました。正確に言うと先調子胴調子の違いではなく竿を振った時に残る振動の収まりの速さに差がありました。良い竿と呼ばれる竿は振ったあとのブランクスの抵抗からくる反発力がうまく竿先に抜けて振動が消えます。しかし安物竿やカーボン含有率の低いもの、バランスの悪いものだといつまでもブルブルしています。
この紫電というモデルはダイワの中堅モデルですから安物ではありません。だから振動の収まりの良さは総じて優秀だったのですが、同じ号数の53モデルと50モデルを振り比べた時に明らかな差がありました。50モデルは振ってもムチのようにスッとすぐに振動が収まります。ところが53モデルは結構な時間ブルブルしていたのです。これには釣具屋の店員も「この差はデカイですね」と言っていました。恐らく竿固有の振動数が関係していたのだと思います。バランスがとても良い。
こうして私は紫電1号50モデルを購入することにしました。持ち重りせず非常に軽くてシャンとして操作性もよく、その上胴調子で、機能性能デザイン共に揃った、まさにパーフェクトな青い磯竿を手に入れた私は嬉しくて早速ウキフカセ釣りに使いました。
ところがこの紫電1-50はメジナをかけてもあまり面白くない竿だったのです。そして私の迷走が始まります。
つづく
関連記事です
自然探検☆水の惑星アウトドア紀行