作家アイザック・ウォルトン「釣魚大全」釣り界の聖書に残された釣り人の性

前回まで、なぜ人は釣りにハマるのか?というテーマについて脳科学から検証してきましたが、忙しない現代社会を生きる私達は日々心を傷つけ、その傷を癒やすために、0に戻るために本能的に少年時代に帰りたがっているとも言えるでしょう。
その衝動の矛先が人によっては買い物やギャンプル、恋愛、釣り、スピード狂などに向き、一線を越えると依存症、中毒になってしまうということですね。
でも人はいずれ刺激に慣れ、理性を外した時にやはり快楽を追求してしまう癖があります。
今回はそんな釣り人の性に悩み苦しんだ、釣り作家たちの心の葛藤をご紹介したいと思います。
前回記事はこちら
↓
なぜ人はハイリスクな状況下でのギャンブル性に興奮するのか?本能と釣りの関係
スポンサーリンク
釣界の聖書「アイザック・ウォルトン 釣魚大全」に書かれた釣り人の闇
まずは釣り作家の大御所、「静かなることに学べ」のアイザック・ウォルトン卿です。
ウォルトン卿( 1593年8月9日 – 1683年12月15日)はイギリスの随筆家、伝記作家です。
このウォルトン卿によって書かれた「釣魚大全」は元々貴族の遊びだった釣りというものを始めて体系化し魅力をまとめた初の書物という位置づけで伝説的存在です。
そのため古くから釣り人のみならず数多くの読者に親しまれてきました。
過去に何度も翻訳化されています。
私が最初に「釣魚大全」を読んだ時は、アイザック・ウォルトン卿の言いたいことがよく分からず「フムフム、とにかく釣りが好きな人だったんだな」ぐらいにしか思わなかったのですが、釣り人の習性を学んだ後に読むと違う解釈で読み取れる部分が多くあり、沢山の釣り人の性を見つけることができました。
本の中でウォルトン卿は次のように述べています。
p67 聖書の中では、釣りはいつも最もよい意味にとられています。
p71 サー・ヘンリーは、「釣りは、退屈な勉強の後にある心の休息、元気を起こさせるもの、悲しみを紛らわすもの、波だった心を静めるもの、激情を和らげるもの、満足をもたらすものであり、それを主張し、実行する者に平和と忍耐の習慣をつちかう」
ここで書かれていることは、「釣りは全てに対する万能薬のようなもの」だということでしょうか。
ただ、殺生を伴う行いという釣りの裏側や、克服すべき現実の生活の課題から目を背けつつ、ひとつの趣味をここまで美化して描くあたり、ウォルトン卿自身に現実逃避の一面があるのではないかと思います。
p89 スポーツが幸先よく始まった…
ウォルトン卿によるこの表現は、「野生動物を捕獲することで得られる娯楽」の意味での「スポーツ」という語が初めて使用された例として、『オックスフォード英語大辞典』でこの部分を引用しているようですね。
スポーツフィッシングという言葉もここから来ているのでしょう。
p312 ジョン・チョークヒルの詩の中で、
『ほかの楽しみは玩具につぎない、嘆かわしいもの』
ウォルトン卿によると、「釣りの持つ魔性の楽しみに比べると、他の遊び程度の刺激では物足らない」ということになるのでしょうか。
釣りにハマると中毒性があり、そしてドーパミンの快楽作用により一種の興奮状態に陥るわけですから、確かに他の楽しみでは自分を満たすことが出来ないという点は、過去の自分の体験と照らし合わせても共感できます。
p337 かつてある人が、「自分より美味しいものを食べている人も、金持ちの人も、いい服を着ている人も羨まない。自分よりたくさん魚を釣る人のほかは誰も羨まない。ただその人のみを羨む」
これは他の事への興味を失い、価値観が狭まることを表しています。依存症の人に見られる症状です。
釣りに夢中になりすぎて家族を失ったという人もいるのです。もはや釣り依存です。
これだけ有名な作家、ウォルトン卿をもってしても釣りという魅力、ハマるメカニズムを上手く表現できなかったのは、まだ脳科学の分野が発達していない時代だったことが大きいでしょう。
また、現代のゆっくりする暇もない世の中と同様、この「釣魚大全」が書かれたのも、ピューリタン革命など激動の時代だったので、ウォルトン卿も心の平安を求め水辺に立っていたのではないでしょうか。
スポンサーリンク
「釣魚大全」に対する他の作家の評価は?
この「釣魚大全」を論評する人たちの中で、憂鬱と情熱―相矛盾する複雑な感情を抱えた近代的自我の詩人バイロン(1788‐1824)は「釣りを残酷」という表現をしています。
また、イギリスの作家・エッセイスト チャールズ・ラム(Charles Lamb、1775年2月10日 – 1834年12月27日)は釣り師を「忍耐強い暴君、柔和な顔をして耐え難い激痛を与える者、冷酷な悪魔」と批判しながら、「この本を読むといつでも人の心は穏やかになる」と述べています。
うーん、やはり過去の作家達は、釣りに対して「善と悪と人間の本能が複雑に入り混じったドロドロとした何か」という評価だったようですね。
釣りはとても原始的な遊びなんですね。
それでは、日本の釣り作家たちは釣りに対してどう感じていたのでしょうか?
それも次回お話しましょう。
つづく
関連記事です
自然探検☆水の惑星アウトドア紀行
コメント
この記事へのトラックバックはありません。














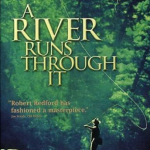


















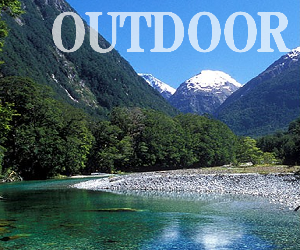
この記事へのコメントはありません。